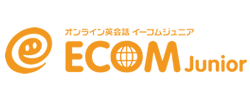大学入試英語試験や、英検試験のシステムは、ヨーロッパ外国語参照指標CEFR(セファール)に対応した評価となっています。
このCEFRが、本家、欧州で、2018年に改定されました。
私は個人的に、すぐに外国基準におっかけたりせず、今のものをベースに、ゆっくり日本独自に指標を発展させてもいいと思うのですが、
1年経った今、
『日本のCEFR基準は時代遅れだ、なんとかしろ!』、
『これでは世界の笑いもの!』。
といった類の批判が多いので、きっと、外圧に弱い日本のこと、
今採用している旧CEFR基準を、新CEFR基準に変えていき、それにあわせて、英検を含めた民間英語試験も対応させていくと予想します。
新CEFRへの変更点
大きくわけて2つあります。
1.CEFRレベルを6から11へ
これまで、易しい方から順番に、
A1, A2, B1, B2, C1, C2
だったのが、
PreA1, A1, , A2, A2+, B1, B1+ B2, B2+, C1, C2, Above C2
とレベル区分が11に増えました。
全く初学者のPreA1 (A0)と、ネイティブレベルのAbove C2を増やし、
中級レベルの、A2, B1, B2を、2分割した。
理にかなっていて、いいと思います。
語学学校現場の立場からも大賛成です!
当校Ecom levelというものがあり、
偶然にも、新CEFRと同じ11段階のレベル区分です。
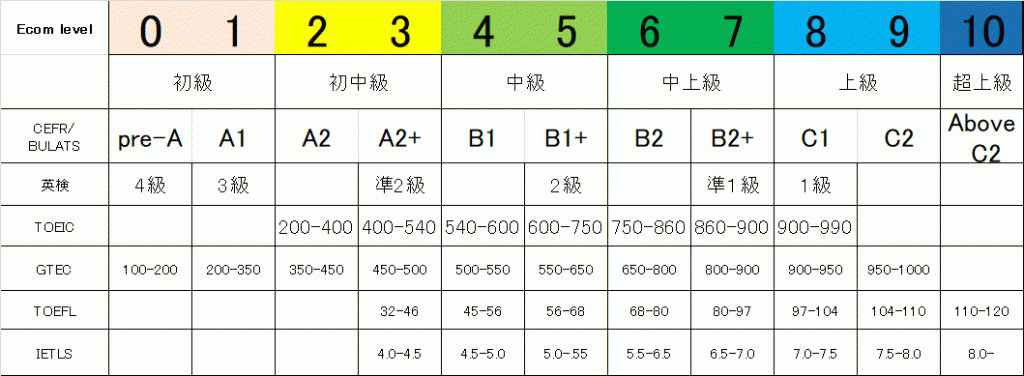
2.4技能から、7技能へ
これまで、単純な、読む、聞く、話す、書くの4技能毎の能力判定だったのが、
下記「7技能」を判定するように変更されました。
Listening comprehension,(リスニング理解)
Reading comprehension, (読解力)
Spoken interaction(やりとりしながら話すこと),
Spoken production(発表形式、プレゼン),
Written interaction,(応答返信、メール、SNS)
Written production, (topic作文, essay)
Mediation(仲介、複数話者との対話)
どのように評価軸が増えたかわかりますか?
「話す」と、「書く」の能力評価を、それぞれ、インタラクティブ、Productionの2つに分けました。
そして、Mediation(調停・仲介)を加えました。
Mediationは、まだ謎が多いのと、日常移民国家欧州とは、日本の状況が違うので、ここでは無視します。
この場合、きちんと評価を出すためには、
話す、聞くが、”発言型”と”会話型”、それぞれ試験問題に対応していく必要があります。
英検のSpeakingは、
ストーリーピクチャー(4コママンガ)や、発言テーマが与えられて、それを発表する形式(Spoken Production)型になっていますが、
きちんと、試験監との英語対話も、採点項目に入っています。
ですので、全く問題ないです。
一方で、英検ライティングは、トピック作文がでているだけです。
これでは、Written interactionを測ることはできないので、
なんらかの形で、Written interactionタイプの英作文も出題として定番化してくると予想します。
いつ頃と予想はできないですが、
いきなり、インタラクティブ・ライティングが出題されて、聞いてないよ~!とならないように、
このような傾向があるのだなと知っておくと、いざ出題されたとしても、おちついてライティング対応できるのでは、と思います。